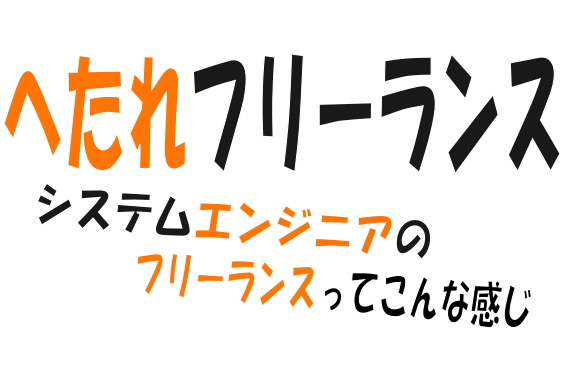フリーランスのシステムエンジニアとして生計を立てるには、自分で主体となって開発案件を見つける事が必要となります。その際、重要になるのが技術経歴書です。技術経歴書の内容は、自分が希望する案件を見つけ、参画できる/できないに大きな影響をもたらします。この記事では、技術経歴書を作成する際のポイントに関して記載します。
技術経歴書は、お客さんとの面談の時にお見せし、内容を説明する必要があります。技術経歴書の説明のポイントに付いては、面談での技術経歴書の説明ポイントの記事をお読みください。
1⃣フリーランスエンジニアにとっての技術経歴書とは
技術経歴書とは、自分をアピールするためのツールです。「システムエンジニアとして何をやってきて、どんな技術サービスをお客さんに提供できるのか」について整理・記載されているドキュメントです。開発案件を探す際、営業さん(エージェント・SES企業)やお客さん(開発案件オーナー)は、この技術経歴書の内容を確認し、開発案件の紹介や面談の実施有無を検討します。
仮に技術経歴書の内容が、営業さんやお客さんにうまくアピールされない場合、開発案件を見つける事が難しくなります。そのため、アピールしたい内容(例:自分の強み)が、お客さんや営業さんに、正確に伝わるように内容を精査して記載する必要があります。
2⃣技術経歴書のポイント
技術経歴書を記載する際のポイントは、以下2点あります。
- 本当の事を記載する。
自分が実際に実行・学習した事を記載する - 相手が見やすいように記載する。
自分のアピールしたい事を、ポイントを絞って、整理して記載する。
経歴書に本当の事を書くのは、当たり前です。そのため、以下の記事では、「2」について記載していきます。
3⃣技術経歴書のテンプレート
以下、実際に私が使っている経歴書を抽象化したイメージになります。実際は、エクセルに記載しています。「①基本情報欄」「②技術サマリ欄」「③経歴欄」の3つのセクションで構成しています。この構成は、見やすさや説明しやすさを意識して作成しました。以下「4⃣技術経歴書の作成ポイント」では、各セクションごとに説明をします。

イメージ上で記載されている内容は、サンプルの記載となり、実際の経歴書に記載されている内容とは、異なります。
4⃣技術経歴書の作成ポイント
①基本情報欄について
名前、保有資格、最寄駅、経験年数など、自分が何者なのかを簡単に記載する欄です。
資格項目には、読み手の目に留まりやすい様に、今注目されている技術の資格を書けるようにするのが良いでしょう。例えば、Cloudに関する資格(AWSなど)やPythonなどの比較的新しい言語の資格が良いでしょう。また、英語は、いつの時代も重宝されるので、TOEICの点数を記載するのが良いです。
経験年数は、お客さんに注目されるので、とても重要な項目になります。嘘はつかず、実際の年数を記載してください。経験年数は、2年~3年以上あれば評価のポイントとなりますが、2年未満だと案件探しに不利に働く場合があります。その場合は、経験が浅いなりに、他のポイントでアピールできる様に工夫が必要ですね。例えば、分かりやすいのは資格の取得になります。後は、お客さんは経験値以外にも、技術者の性格(明るいか など)やコミュニケーション力を見るので、そういった人間力を日々意識し高める事が良いです。
最寄駅は、営業さん(エージェント、SES企業)に見せて、最寄駅から近い場所の案件を紹介してもらったり、面談の時にプロジェクト現場と最寄駅が近い場合、お客さんへのちょっとしたアピールポイントとなります。
②技術サマリ欄について
実践経験がある技術・開発環境(OS、言語)などを記載する欄です。
これまでの案件で実践してきた技術や言語を、キーワードレベルで記載し、読み手が経歴書を見た時にぱっと目に入る事を意識しています。これにより、読み手に「この言語できるのね」「DBはこれができるのか」と思ってもらい、興味を引き出す事が目的です。
上記のサンプルでは、「OS」、「プログラム言語」、「DB・サーバ」項目以外に、「開発工程」や「職務(役割)」の項目を設定しています。理由は、様々な開発工程や役割を経験している部分をアピールし、プロジェクトの管理(進捗管理など)や調整(チーム間調整、ファシリテーションなど)を行う案件を狙っているからです。設計・プログラミングも楽しいですが、今の自分には、プロジェクトの管理や調整に関連する案件への興味が強く、そのような理由で「開発工程」「職務(役割)」の項目を入れています。
と言うように、都度自分のやりたい案件(言語、役割、環境など)を念頭に置いて、技術サマリ欄は項目や記載内容を変えています。
③経歴欄について
今までどのような案件に参画し、どんな役職、どんな技術を使って作業を行ってきたかを記載する欄です。要は、自分の経験値です。「自分は、今までの案件ではこのような事をやってきました。なので、この案件に貢献できます」をアピールします。
この欄は、お客さんが最も注目する欄です。なぜならお客さんは即戦力が欲しいので、様々な経験をしている人材を求める傾向があるからです。最も大切な欄と言う事もあり、面談では経歴書を説明する際に、最も時間を使います。
この欄に記載している項目は以下の通りです。「誰(お客さん)に対して、どのようなサービス(技術)を提供したか」を記載します。
- お客様概要
どの様なビジネスを行っているお客様か、を一言で記載します。
例えば、精密機器を製造・販売を行っているお客様、といった感じです。 - 案件概要
どんな案件かを、一言で記載します。
例えば、クレジットカード決済システムの構築、という感じです。 - 役職
上記で記載した案件の中で、どの立ち位置(役割)だったかを記載します。
例)PG,リーダ、PMOなど - タスク
どんなタスクを行ったかを記載します。1案件に付き、主なタスクを3つ記載しています。3つの理由は、全て記載すると経歴書が読みにくくなり、読み手に響かない内容になってしまうからです。 - 参画期間
案件ごとに、参画した期間を記載します。この項目は、参画期間が長いと、お客さんへのアピールポイントとなります。なぜなら、1つの案件で参画期間が長いと、それだけ実力があり、また案件の他メンバーとの交流・関係を構築できる人材と思われるからです。
その他
技術経歴書を作成する際は、「面談でお客さんに説明しやすい」、「営業さんが読みやすいか」を意識しながら作成するのが良いです。特に「履歴欄」は、面談では重要な部分になるので、注意して記載する事をお勧めします。
5⃣まとめ
この記事で紹介した技術経歴書のレイアウトや内容は、自分の希望案件や説明しやすさを意識して構成や項目を決めているので、みなさんも自分に合った経歴書を作成するのが良いです。技術経歴書をいかに自分の分身にするか、がとても重要になります。